地震が起こったときにダメージを受ける部分として様々なことが考えられますね。
自宅で言えばタンスや大型家電の冷蔵庫やテレビが倒れたり、小物だと花びんや食器類が揺れによって割れてしまうこともあります。揺れがひと段落した後の片づけは嫌なものですね。
しかし、より大きな視点で言えば電気・ガス・上下水道設備のダメージが継続的かつ受ける被害としては大きく、これらインフラ(ライフライン)設備のダメージを元に戻すまでの時間が気になるところです。
今回はインフラ設備が被害を受けたあとの復旧するまでの期間と自ら対策しておくべき優先順位について考えていきます。
過去の地震災害での復旧にかかった時間と日数
もう13年前になってしまいましたが、平成になってからの大きな地震災害で真っ先に思い当たるのは2011年3月11日の東日本大震災です。
地震の規模はマグニチュード9.0で最大震度7を記録し、人的な被害も死者・行方不明者を含めると約2万人と甚大だったことを思い出されるでしょう(地震以外の災害情報については以下の過去記事を参照ください)。
その後、他にも北海道、熊本でも大きな地震がありましたが平成に入ってから地震での被害が起こった後に電気・ガス・水道などインフラ設備と呼ばれるものが復旧までにかかった日数がどのくらいかご存知でしょうか?
東日本大震災(2011年)の場合
厚生労働省が発表した報告書(東日本大震災水道施設被害状況調査報告書(平成23年度災害査定資料整理版))によると次のようになっています。
なお、停電は850万世帯、ガス不供給は46万世帯、断水は230万世帯です。
| インフラ | 当日 | 1日後 | 3日後 | 1週間後 | 2週間後 | 3週間後 | 5週間後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気 | 10.8% | 52.2% | 78.8% | 98.6% | - | - | - |
| ガス | 0% | - | - | 9% | 13% | 42% | 99% |
| 水道 | - | - | 50% | 66% | 88% | 99% | - |
復旧が早い : 電気 >> 水道 > ガス:遅い
インフラの復旧にはなぜ時間が必要か?
地震災害では当然ですが地面ごと揺れるため、一般的に地下に埋められている水道管やガス管、通信ケーブル、地上に設置されている電柱や電線なども揺れによるダメージを受けてしまいます。
電線や電柱など電気設備の復旧
 電力供給設備は発電所から高圧線を通して、変電施設へ電柱へ、そして各家庭へ電気を供給しています。一部の地域では美観や安全性の点から地中へ埋めているところもありますが、ほとんどは地上へ出ています。
電力供給設備は発電所から高圧線を通して、変電施設へ電柱へ、そして各家庭へ電気を供給しています。一部の地域では美観や安全性の点から地中へ埋めているところもありますが、ほとんどは地上へ出ています。
地震が発生した場合、一定の震度以上では発電所の安全装置により自動的に発電・送電を停止させます。また発生の規模によって家屋の倒壊や電柱自体が倒れてしまうなどにより電線が切れてしまうこともあります。
復旧には、被災した電線を修理・接続し漏電が起こっていないことを確認した上で、電力供給を再開することになります。
基本的に電気設備は地上に露出していますので、地上に埋められている水道管やガス配管に比べると、途切れている箇所の特定やチェックの他に地中の掘り返し/埋め直すこと必要がないため復旧が早くなります。
上下水道の配管復旧
 上水道や下水は地中に埋められており、大きな配管の部分はトンネルのような人が立って歩けるくらい大きいところもありますが、各家庭への供給ラインは道路の地中部など掘り返して配管を埋めています。
上水道や下水は地中に埋められており、大きな配管の部分はトンネルのような人が立って歩けるくらい大きいところもありますが、各家庭への供給ラインは道路の地中部など掘り返して配管を埋めています。
被災で配管が破損し漏水したときは壊れた箇所の特定が必要となりますが、地中のため”この辺りのはず”までは分かっても特定となるとアスファルトなどを掘り返し確認する必要があります。
また漏水が1箇所でも残った状態では水の供給ができず、エリア内の配管をすべてチェックした上での再供給となりますのでどうしても時間が掛かってしまいます。
状況としては致し方ないものの水は人が生きていく上で最も重要なものです。水が人にとって1日あたり必要なのかについては以下の過去記事を参照ください。
なお断水時の備蓄、節水対策は以下の記事が参考になると思いますのでよろしければどうぞ。
参考 災害時の衛生管理には”水のいらないシャンプー”等を備蓄しておくと安心
ガス経路の復旧
 都市ガスの場合、水道管と同様に地中に埋められています。基本的に水道設備と同様な対応となるため時間が掛かります。
都市ガスの場合、水道管と同様に地中に埋められています。基本的に水道設備と同様な対応となるため時間が掛かります。
これに加えてガス設備では、可燃性ガス、かつ目視で漏れを確認できません。水道管の場合は漏れていれば水があふれる、下水では排水のにおいがするなど分かりやすいのですが、ガスでは臭気はあるものの目視できないため専用の機械でチェックする必要があります。
またガスは可燃性のため濃度が高くなってしまうと爆発、炎上する可能性もあります。
このため配管を再接続し修理した後も本当にガス漏れが発生していないかチェックし安全が確認できて始めて再供給されるため、時間が掛かってしまいます。
復旧までの日数で見えてくる対策の順番
ライフラインとしてのインフラ設備が復旧するのは、早い:電気 >> 水道 > ガス:遅いとなります。
地震の規模にもよりますが「電気」は数日中で使用できるようになると考えられるため、通信手段や情報収集用のスマートフォンが電池切れしない程度を確保できれば良いかもしれません。
「水道」は数日~3週間程度が復旧に必要であり、人体に欠かせない水は最優先で確保、できればペットボトルなど備蓄しておいた方が良いでしょう。
「ガス」は1週間~1ヶ月程度が必要となり、復旧に最も時間はかかりますがガスの主な用途として食事の調理やお風呂、シャワーで使用されると思います。使えなければ当然に不便ですが代用が可能と考えられます。
重要度大:水の確保と節約 >> 電力 ≧ ガス
まとめ
- 地震で被災したあと、ライフラインの復旧は「早い:電気 >> 水道 > ガス」の順番である。
- 被災設備の交換やチェックにより復旧までの日数がかかり、特にガスは漏れの確認で時間が必要。
- 一般家庭で対策すべき順番は「重要大:水 >> 電気 ≧ ガス」が良いと考えられる。
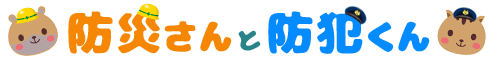










コメント
[…] 出典はこちら。 […]